契約時の確認でトラブルを防ぐ!仮契約からの注文住宅づくりの流れ
公開:2024.07.26 更新:2025.04.17
仮契約は家づくりの初期段階で、設計プランや費用の合意が行われます。仮契約後は詳細な打ち合わせと建築確認申請を経て、本契約に進みます。仮契約時には申込金の取り扱いやキャンセル条件を確認し、契約書に総額費用や地盤調査の結果を明記することが重要です。予算内での仕様確認と、キャンセル条件の確認も忘れずに行いましょう。
目次
注文住宅メーカーを選ぶ流れ

注文住宅を建てるにあたり、住宅メーカー選びは非常に重要です。理想的な家を実現するためには、自分たちの希望に合ったメーカーを慎重に選ぶ必要があります。こちらでは、注文住宅の住宅メーカー選びの流れを紹介し、理想の住まいを手に入れるための具体的なステップを解説します。
◇土地と建物の予算配分を決める

注文住宅を建てる最初のステップは、土地と建物にかける予算をしっかり決めることです。住宅メーカーを選ぶ際は、予算に合ったメーカーを選ぶことが大切です。
土地がすでに決まっている場合は、まず、その土地に適した建物の価格帯を設定する必要があります。土地の購入前であれば、土地と建物を合わせた総予算をしっかりと計算し、その中でどれだけの金額を土地、建物に振り分けるかを決めることが必要です。
予算配分の基本として、土地代と建物代を均等に分ける方法もありますが、地域や土地の価格によってはこのバランスを調整する必要が生じます。例えば、土地の価格が高い場合、建物の予算を抑えるために、シンプルで機能的なデザインを選ぶことが重要です。反対に、土地代が比較的安い場合、建物に使える予算を増やし、豪華な仕様を取り入れることが可能となります。
◇カタログを取り寄せて理想の住まいをイメージする

予算が決まったら、次は住宅メーカーのカタログを取り寄せて、理想的な家のイメージを膨らませることが重要です。カタログでは、各メーカーが提案するデザインや間取り、使用する素材などの特徴を知ることができます。カタログを参考にしながら、自分たちのライフスタイルに合った家を想像してみましょう。
カタログを見ていると、各メーカーの特徴がよくわかります。例えば、収納に優れた家を希望するなら、収納スペースに特化した設計をしているメーカーを選ぶと良いでしょう。また、カタログだけでなく、メーカーのウェブサイトやオンラインギャラリーを利用して、さらに多くの情報を収集することもおすすめです。
◇住宅展示場で実物の家を体感する

カタログで理想の家のイメージが固まったら、実際に住宅展示場に足を運び、実物の家を体感することが次のステップです。住宅展示場では、カタログやインターネットではわからない空間の広さや質感、設備の使い心地を直接確認できます。また、実際に家を見て歩くことで、具体的なイメージが湧き、どのメーカーが自分たちの理想に近い家を作れるかが見えてきます。
展示場を訪れた際は、家の内装や外装だけでなく、スタッフの対応にも注目しましょう。スタッフから直接説明を受けることで、そのメーカーのサポート体制やこだわりを知ることができます。展示場では、具体的な質問を準備しておき、気になる点をスタッフに聞いてみるとより有益です。
◇気に入った2~3社に見積もりを依頼する
最後に、気に入った住宅メーカーが決まったら、2~3社に見積もりを依頼し、実際にかかる費用を比較しましょう。見積もりを取得することで、各メーカーが提供するサービスや追加オプションの内容、価格を比較することができます。見積もりの段階で、どのメーカーが最もコストパフォーマンスに優れているかがわかります。
見積もりを依頼する際には、なるべく詳細な希望を伝えることが重要です。間取りやデザイン、使用する設備や素材について、自分たちが希望する内容を明確に伝えることで、より正確な見積もりをもらうことができます。
【あわせて読みたい】
▼注文住宅の趣味部屋で暮らしを豊かに!理想の部屋作りのポイント
住宅メーカーが決まった後は?仮契約後の家づくりの流れ

仮契約は家づくりの初期契約で、設計プランや費用を確認します。申込金が必要で、本契約時に充当されるか返還される場合があります。仮契約後は詳細打ち合わせ、建築確認申請、本契約を経て工事開始、地盤調査、基礎工事、最終検査の流れで進行します。
◇仮契約とは

注文住宅の仮契約とは、本契約(請負契約)前に施主と住宅会社が交わす暫定的な契約で、法的拘束力があるため注意が必要です。主な目的は、プラン作成や詳細設計の開始、土地の仮押さえ、他社への流出防止、調査業務の着手などです。
契約時には申込金や設計料として数万円~数十万円が発生し、本契約に進めば工事費に充当されますが、契約に至らない場合は返金されないこともあるため、契約内容の確認が重要です。
◇仮契約後の流れ
仮契約後は、詳細な設計打ち合わせが始まります。設計プランが決まったら、建築確認申請を行い、建築許可を取得します。このプロセスには通常1ヶ月程度かかります。
次に、本契約が行われ、仮契約の内容を基に正式な契約書が作成され、最終的な費用や工期などが確認されます。
本契約後は工事が開始され、地盤調査や基礎工事が行われ、建物の具体的な形が見えてきます。工事中は進捗状況を定期的に確認し、工事が完了したら最終検査を経て引き渡しとなります。
仮契約後の詳しい流れは、以下のとおりです。
本見積り
仮契約後は、間取りや設備、仕様をさらに詳細に決定し、本見積りを依頼します。この際、平面図、立面図、仕上表、仕様書、見積書を照らし合わせ、抜け漏れがないか慎重に確認することが重要です。特に、本体工事費に加え、付帯工事費や諸費用が正しく含まれているかを確認することを忘れないようにしましょう。
また、本契約後にプラン変更を行うと、追加費用や工期の延長が発生する可能性があるため、構造に関わる部分の仕様は本契約前にしっかり確定させることが大切です。
住宅ローンの検討・事前審査
具体的な間取りやプランを決定するタイミングで、住宅ローンの検討と事前審査を進めます。金利タイプや返済期間を自分たちのライフプランに合わせて選び、無理のない借入金額と資金計画を立てることが重要です。
もし建築会社が提携しているローンを利用する場合、手続き代行をしてくれることもありますが、代行手数料が発生する場合があるため、事前にその費用を確認しておくことが大切です。
本契約(建築工事請負契約)
間取りや予算が確定し、本見積りが完成したら、依頼先と本契約(建築工事請負契約)を締結します。契約書には、発注者と請負者の氏名、工事内容、請負代金、支払方法、工事着手と完了の時期、引き渡し日などの重要事項が記載されています。契約時には手付金として建築費の約10%を支払うのが一般的です。
また、本契約では工事請負契約書、契約約款、設計図書、仕様書、工事費見積書などの書類が必要となり、契約金の支払いに伴い印紙税の負担も発生します。支払方法や引き渡しのスケジュールなど、契約内容を細かく確認し、後のトラブルを防ぐことが大切です。
建築確認申請
建築確認申請は、建築する住宅の間取りや仕様が建築基準法などの法規に適合しているかを審査するもので、通常は依頼先の施工会社が代行してくれることが多いです。申請が通ると、柱や壁の位置、窓の大きさや配置など、建築基準法に関わる部分の変更ができなくなるため、事前に間取りや仕様をしっかり確認しておくことが重要です。
スムーズな家づくりのためにも、細部まで慎重にチェックし、必要に応じて申請前に修正を依頼しましょう。
【あわせて読みたい】
▼間取りで後悔しないために!家事動線の重要性と注文住宅の設計ポイント
注文住宅の仮契約に関するよくある疑問

注文住宅を購入する際、仮契約に関する疑問が生じることがよくあります。仮契約は契約の初期段階であり、本契約とは異なる性質を持っていますが、どこで違いが出るのか、またキャンセル時にどうなるのかなど、詳細を理解しておくことが重要です。今回は、注文住宅における仮契約に関するよくある疑問について解説します。
◇仮契約と本契約の違いは?
仮契約は、住宅メーカーとの取引を本格的に進める前に交わすものであり、主に見積もりや間取りプランの作成、詳細な打ち合わせの前段階として位置づけられています。仮契約を結ぶことによって、住宅メーカーは一定の手間やコストをかけてプランを提案します。仮契約は、一般的には、最終的な本契約に比べて拘束力は限定的です。仮契約には法的拘束力が発生するかどうかは、内容や契約書に記載された条件によって異なります。
一方、本契約は、正式に住宅の建設を進めるための契約であり、法的拘束力が発生します。本契約が締結されると、住宅メーカーは正式に住宅の建設を開始する義務を負うことになります。仮契約はあくまで取引の準備段階であるため、最終的な建設契約に進む前に仮契約を解消することも可能ですが、本契約は解消が難しく、キャンセルには違約金が発生することがあります。
◇仮契約時に支払う申込金の扱いは?
仮契約が結ばれるタイミングでは、申込金の支払いが求められることがあります。これは、住宅メーカーに対してプランの作成や見積もりを依頼するために必要な金額です。申込金は、一般的に5万〜10万円程度が目安となります。この金額は、後の本契約時に手付金として充当されることが多いですが、契約書に明記された条件に基づき、返金がある場合や適用される方法が異なることもあります。契約前に、申込金がどのように扱われるかをしっかりと確認しておくことが重要です。
◇キャンセル時の違約金は発生する?

仮契約を締結した後、万が一キャンセルした場合、違約金が発生するのか心配になる方も多いかもしれません。仮契約は法律的に強制力がないため、基本的にはキャンセルをしても違約金は発生しないことが一般的です。
しかし、申込金については契約書に定められた規定に従い、一定の条件で返金されない場合もあります。また、キャンセル後に、すでに費用がかかっている場合(例えば、間取りプランの作成や特別な提案など)には、その分の費用を支払うことを求められることもあります。
仮契約を締結する際には、キャンセル条件についてもしっかり確認し、万が一キャンセルする場合にどのような対応が取られるのかを理解しておくことが大切です。
◇キャンセルした場合の申込金

通常、仮契約をキャンセルした場合、申込金は返金されるのが一般的です。しかし、仮契約に伴うプラン作成などの費用が発生している場合、その費用が申込金から差し引かれることもあります。具体的な返金条件は契約書に明記されているため、契約前にしっかり確認しておくことが必要です。
なかには、キャンセル後に申込金が返金されない場合があります。契約前に返金条件や費用負担に関する詳細を十分に確認し、不安があれば事前に住宅メーカーに問い合わせることをおすすめします。
【あわせて読みたい】
▼新築でも古民家風の注文住宅は建てられる!魅力とポイントを解説
仮契約する際の注意点

仮契約時の申込金は、本契約時に充当されるのが一般的ですが、キャンセル時に返却されないこともあります。契約書で申込金の取り扱いを確認し、キャンセル条件を把握することが重要です。契約を急かされる場合は慎重に対応し、他のメーカーと比較検討することが大切です。
◇キャンセルした場合の申込金

仮契約時に支払う申込金は、本契約時に充当されるのが一般的ですが、キャンセルした場合に返却されないこともあります。仮契約を結ぶ際には、申込金の取り扱いについて契約書でしっかり確認し、納得しておくことが大切です。
特に、仮契約後に契約解除の可能性がある場合には、返金条件やキャンセル料について詳細に把握しておく必要があります。
◇契約を急かす住宅メーカーには要注意
住宅メーカーが契約を急かす場合は注意が必要です。十分な検討期間がないまま仮契約を促されると、設計や費用について不明瞭な点が後々のトラブルの原因になります。
信頼できるメーカーは、契約前にしっかりと説明を行い、顧客の質問や不安に丁寧に対応します。契約を急かされる場合は、一旦冷静になり、他のメーカーと比較検討する時間を確保しましょう。
【あわせて読みたい】
▼注文住宅の予算オーバーを回避!賢く費用を抑える方法を徹底解説!
トラブルにならない為に!仮契約の際に確認すべきこと

仮契約時は契約書で総額費用や申込金の扱いを確認し、返金条件を明記することが重要です。具体的な間取りや設備の希望を伝え、予算内でのプランを固めることで、予算オーバーを防ぎ、理想の注文住宅に近づけます。
◇契約書で確認すべきこと
仮契約を結ぶ際には、契約書の内容を詳細に確認することが重要です。特に総額費用の確認は欠かせません。総額費用には建築費用だけでなく、設計費用や申請費用、付帯工事費用などが含まれるため、すべての項目を確認しておく必要があります。
また、申込金の扱いについても明確にすることが重要です。申込金が本契約に充当されるのか、キャンセル時に返還されるのかを確認し、返金条件を契約書に明記しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
◇予算オーバーを防ぐために

仮契約前には、できるだけ具体的に間取りや設備の希望を伝えることが大切です。具体的な設計が難しい場合でも、希望を伝えることで予算オーバーを防げます。希望する間取りや設備のグレードを明確に伝えることで、住宅メーカーはそれに基づいた見積りを作成します。
予算内で希望を叶えるためには、仮契約の段階で具体的なプランを固めることが重要です。また、予算内で希望を最大限に実現するために、優先順位を明確にすることも必要です。
仮契約で確認すべきことを把握し、納得のいく契約を進めることで、理想の注文住宅に一歩近づくことができます。
【あわせて読みたい】
▼建売住宅と注文住宅の違いは? 迷っている場合にやるべきこと
納得の家づくりのために~本契約前に確認すべきこと

地盤調査は建物の安全性を確保するために必須で、追加基礎工事が必要になることもあります。予算確定や仕様の決定も本契約前に行い、予算オーバーや予期しない出費を防ぎましょう。また、キャンセル時の違約金条件も契約書で確認することが重要です。
◇地盤調査

建物を建てる前に、土地の地盤が建築に適しているかどうかを確認する地盤調査は非常に重要です。地盤の状態によっては追加の基礎工事が必要になり、その費用も発生します。
地盤調査は建物の安全性を確保するための必須ステップであり、本契約前に実施し、その結果を基に設計を進めることが重要です。地震が多い地域では、特に地盤の強度や安定性を確認することが重要です。
◇予算の確定
本契約前には、建物の予算を確定させることが不可欠です。建物本体の費用だけでなく、設備やオプション、外構工事の費用も含めた総額を確認する必要があります。予算オーバーを防ぐために、細かな仕様や設備のグレードも決定しておくことが重要です。
注文住宅では仕様の変更が費用増加につながることが多いため、すべての項目を本契約前に確定させ、書面に残しておくことが大切です。これにより、予期しない出費やトラブルを防ぐことができます。
◇スケジュールと工事が遅延した場合の対応
工事スケジュールは、着工日・工事完了日・引き渡し日を明確に設定し、契約時にしっかり確認しておきましょう。万が一の遅延に備え、対応策や違約金の有無についても事前に把握しておくと安心です。
また、建築費用の支払いは、契約時・着工時・棟上げ時・引渡し時など複数回に分かれるのが一般的です。契約内容によって支払いスケジュールや金額の配分が異なるため、資金計画とあわせて事前にチェックし、スムーズな進行を心がけましょう。
◇アフターサービスや保証内容
住宅の引き渡し後は、不具合が発生した場合に備え、保証内容や範囲、アフターサービスの詳細を確認することを推奨します。注文住宅では、施工会社が最低10年の保証を提供することが義務付けられていますが、保証の適用条件や範囲に違いがあるため、細かくチェックすることが大切です。
また、自然災害などの不可抗力による工事中断時の対応や取り決めについても、事前に確認しておくことで、予期せぬトラブルに備えることが可能です。
◇キャンセルした場合
本契約後にキャンセルする場合の違約金についても確認しておく必要があります。工事が進行しているため、キャンセル時の費用負担が大きくなることがあります。違約金の金額や条件については契約書に明記されているため、事前にしっかりと確認し、納得した上で契約を進めることが重要です。
◇違約金はどれくらい?
本契約(工事請負契約)は、住宅の着工前に結ぶもので、契約時には住宅価格の5~10%程度の手付金を支払うのが一般的です。
契約後にキャンセルする場合、手付金を放棄すれば解約できますが、手付解除の期限を過ぎると違約金が発生する可能性があるため注意が必要です。
また、契約後に地盤調査や設計、改良工事などがすでに完了している場合、その分の費用を請求されることもあります。トラブルを避けるためにも、契約時に違約金の条件やキャンセル時の費用負担をしっかり確認しておきましょう。
【あわせて読みたい】
▼バリアフリー住宅とは?設計のポイントと熊本市のリフォーム事例
注文住宅の契約時によくあるトラブルとは?

注文住宅の契約は、理想の家を形にする大切なステップですが、契約内容の確認不足や予期せぬ追加費用、工期の遅れなどのトラブルが発生することもあります。特に、住宅ローンや工事内容の変更、違約金の条件などは契約前にしっかり確認しておくことが重要です。
◇工事の追加や変更
注文住宅では、契約後の仕様変更や工事の追加によって、想定以上の費用がかかることがあります。契約時に「細かい部分は後で決めましょう」と言われ、そのまま工事を進めた結果、予算を大きく超えてしまうケースも少なくありません。
工事が始まってからの変更は可能ですが、選択肢が限られるため、契約前にできるだけ詳細なプランを決めておくことが大切です。契約後に変更や追加を検討する場合は、スケジュールや費用を事前に確認し、慎重に判断しましょう。
◇工事の遅延
工事の遅れにより、引っ越しのスケジュールが合わなくなるケースは珍しくありません。賃貸の解約日とズレが生じると、仮住まいの家賃や引っ越し費用が増え、受け取った遅延損害金では補いきれないこともあります。
工事の遅延は、天候や予期せぬトラブルによって発生する可能性があるため、遅延損害金の条件や補償内容を事前に確認しておくことが大切です。スケジュールの遅れに備え、余裕を持った計画を立てることで、トラブルを最小限に抑えられるでしょう。
◇住宅ローン

注文住宅の契約時には、住宅ローンの審査や契約内容に関するトラブルが発生することがあります。特に、ローン特約を契約書に記載していても、金融機関名が明記されていないと、「金利の高い金融機関なら審査が通る」といった理由で契約解除ができないケースがあります。
契約時には、利用する金融機関名・融資額・ローン特約の期限が正しく記載されているかをしっかり確認しましょう。事前に細かくチェックし、ローントラブルを未然に防ぐことが大切です。
【あわせて読みたい】
▼1000万円台の家づくりのポイントと注意点!施工事例も紹介
熊本でおすすめの注文住宅会社を紹介
熊本で理想の注文住宅を建てるなら、地域の気候や風土に適した高品質な住まいを提供するハウスメーカー選びが重要です。耐震性や断熱性、デザイン性に優れた家づくりはもちろん、コストパフォーマンスやアフターサポートも重視すべきポイントです。
◇新産住拓株式会社

新産住拓は、熊本で50年以上にわたり地域に根ざした家づくりを手がける注文住宅会社です。最大の特徴は、熊本の気候や風土に適した「木の住まい」へのこだわりです。人吉・球磨などの地元産の木材を丁寧に加工し、快適で健康的な住環境を提供してきました。
| 会社名 | 新産住拓株式会社 |
| 所在地 | 〒861-4101 熊本県熊本市南区近見8-9-85 |
| 電話番号 | 0120-096-112 |
| 公式ホームページ | https://shinsan.com/ |
特に、無垢材の香りがもたらすリラックス効果や、森林浴による健康効果など、自然素材の特性を活かした住まいづくりに力を入れています 。また、耐震等級3の最高等級を取得するなど、安全性と快適性を兼ね備えた住宅を提供し、持続可能な社会の実現にも貢献しています 。「熊本になくてはならない会社」を目指し、地域社会と共に歩み続けています。
新産住拓株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇松栄住宅株式会社
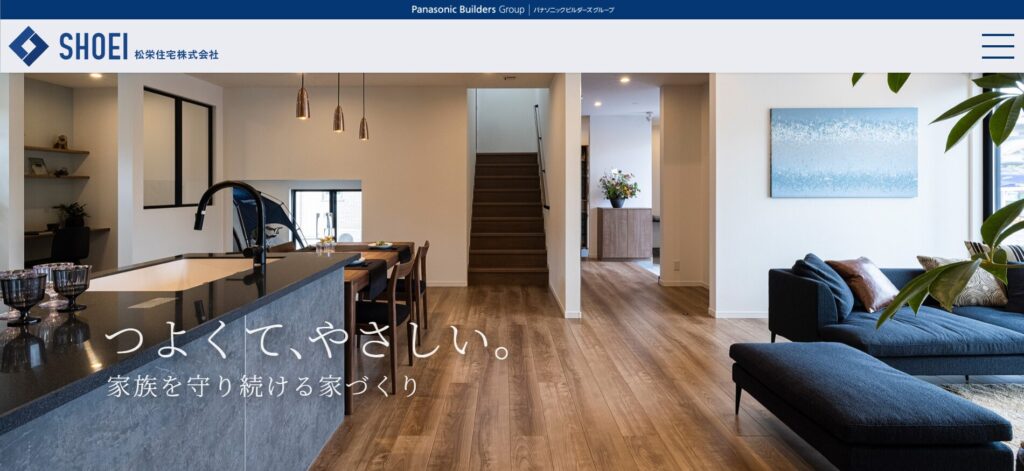
松栄住宅株式会社は、熊本県で長年にわたって地域密着型の家づくりを行っている住宅メーカーです。特に「お客様第一」を掲げ、細部にわたるサポートときめ細かな対応が特徴です。住まいづくりにおいては、耐震性や省エネルギー性能を重視しており、最新の建築技術を取り入れた安心・安全な住宅を提供しています。
| 会社名 | 松栄住宅株式会社 |
| 所在地 | 熊本県熊本市南区田迎1-7-14 松栄ビル3F |
| 電話番号 | 096-379-4676 |
| 公式ホームページ | https://shoei.house/ |
さらに、快適でエコな暮らしを実現するため、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)の設計にも力を入れています。家族のライフスタイルに合った多彩なプランを提案し、住む人の満足度を最優先に考えた家づくりを行っています。
こちらも併せてご覧ください。
◇株式会社ヤマックス

株式会社ヤマックスは、熊本を拠点に注文住宅を手がける企業で、家づくりの品質と性能にこだわり続けています。特に、断熱性や気密性に優れた「快適な住まい」を提供し、居住者の快適さを最大限に引き出します。耐震等級3の高い耐震性能を持ち、安全な住環境を提供しています。
| 会社名 | 株式会社ヤマックス |
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺3-9-5 |
| 電話番号 | 096-381-6411 |
| 公式ホームページ | https://www.yamax.co.jp/ |
さらに、環境にも配慮し、エネルギー効率の良いZEH住宅の普及にも積極的です。デザイン面でも自由度が高く、家族一人ひとりのニーズに合った、魅力的で機能的な家づくりを実現しています。家族の幸せを支える住まいを提供する企業です。
こちらも併せてご覧ください。
仮契約は住宅メーカーとの初期契約で、家づくりの方向性や費用について合意する段階です。仮契約後は詳細な設計打ち合わせが行われ、設計プランが決まると建築確認申請を行い、建築許可を取得します。
その後、本契約が行われ、正式な契約書で費用や工期が確認されます。工事開始後は地盤調査や基礎工事を経て、最終検査の後に引き渡しとなります。
仮契約時の申込金の取り扱いやキャンセル条件を確認することが重要です。また、契約を急かすメーカーには注意が必要で、十分な検討と比較が求められます。
契約書には総額費用や申込金の取り扱い、地盤調査の実施、予算の確定などを明確にし、後のトラブルを防ぎましょう。
本契約前に地盤調査を実施し、予算を確定させ、キャンセル条件も確認することで、安心して家づくりを進めることができます。
熊本で家を建てるなら
当メディアおすすめハウスメーカーを見る

