自然災害の多い熊本で建てる台風や地震に強い注文住宅
公開:2024.05.29 更新:2025.04.11
九州は自然災害が多く、熊本地震や集中豪雨などの大規模な災害が頻発しています。浸水により家具や家電が損傷し、地盤の劣化も懸念されます。熊本では高気密・高断熱の家が適しており、耐震性も重視されます。長期優良住宅建築計画認定制度に基づいた家づくりが安心で、耐震性や居住性などの要件を満たすことが求められます。
目次
九州で自然災害が多い理由と過去の災害

九州は台風の経路にあり、活火山が多く、プレート境界に位置するため、自然災害が多い地域です。過去には2016年の熊本地震や2020年の豪雨など、大規模な災害が頻発しています。
◇九州で自然災害が多い理由
九州は、日本の中でも自然災害が多い地域として知られています。その理由として挙げられるのは、九州が台風の経路であることです。夏から秋にかけては毎年多くの台風が九州に接近・上陸するため、どうしても強風や豪雨、高潮などの被害を受けやすくなってしまいます。
さらに、九州地方には阿蘇山や桜島、霧島山などといった活火山が多いため、火山活動に伴う噴火や火山灰の影響を受けやすいのが九州の特徴です。
それだけではなく、ユーラシアプレートとフィリピン海プレート、そして太平洋プレートの境界に位置しているため、プレートの動きによって地震の被害に遭いやすい地域でもあります。
◇九州で過去に起きた大規模災害

九州で過去に起きた大規模の自然災害としては、熊本地震と有明海沿岸地震、そしてたびたびの集中豪雨が記憶に新しいところです。2016年に発生した熊本地震では、死者数276名、家屋全壊が8,667棟の被害が出ました。
2020年7月に熊本県南部で起こった豪雨や、2018年の集中豪雨、2012年の北九州豪雨でも、死者を出す甚大な被害が起きています。
【あわせて読みたい】
豪雨や台風による住宅への影響

九州が台風の被害を受けた場合、風速20m/s以上でビニールハウスや屋根が飛び、30m/s以上で金属屋根や壁材が剥がれることがあります。台風による豪雨で河川が氾濫し、浸水により建物が損傷し地盤が軟弱化する恐れもあるでしょう。
◇台風の風による被害

九州は台風の通り道になっており、毎年台風の季節になると必ず台風による被害に見舞われる地域です。
特に平均風速が20m/sを超えるようになると、ビニールハウスが破れたり、屋根瓦やかやぶき屋根が飛散したりする恐れが出てきます。それだけではなく、固定されていない小屋などが転倒するケースも珍しくありません。
さらに平均風速が30m/sを超えると、金属屋根材が剥がれたり、壁材が剥がれて飛散したりする恐れも出てきます。
◇豪雨による浸水の影響
台風の通過する地域では、水害にも注意しなければなりません。河川の氾濫や排水不良が発生すると、住宅の床下や床上まで水が入り込むことがあります。浸水によって家具や家電が損傷するばかりか、建物の構造自体も劣化します。
浸水が長時間に渡ると地盤が軟弱化し、住宅の基礎部分が沈下する、あるいは建物が傾いてしまうこともあります。
【あわせて読みたい】
▼家づくりの心強いパートナー!熊本でおすすめの工務店・ハウスメーカー3選
災害に強い家の特徴

災害に強い家とは、地震や台風、水害などの自然災害に対して高い耐久性を備え、安全に暮らせるよう設計された住宅のことを指します。これを実現するためには、耐震・耐風・耐火・防水といった複数のポイントを考慮することが重要です。
◇地震対策
地震対策としては、まず「耐震等級3」の住宅を選ぶことが非常に重要です。耐震等級とは、建築基準法で定められた建物の耐震性を3段階で評価する基準であり、その中でも「耐震等級3」は最高ランクに該当します。
具体的には、阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大地震が発生しても、建物が崩壊するリスクを大幅に軽減する設計となっています。この耐震等級3の建物は、消防署や警察署といった災害時の拠点となる建築物と同等の耐震性を持つとされ、住宅選びの際に大きな安心材料となります。
さらに、耐震性だけでなく、「制震」や「免震」といった技術を取り入れることで、地震の際の揺れそのものを抑えることが可能です。
制震技術では、建物に特殊な装置を設置し、地震の揺れエネルギーを吸収する仕組みが採用されています。この技術により、建物全体の揺れを効果的に低減し、家具の転倒や構造体のダメージを防ぐことが期待されます。
一方で、免震技術は建物と地面の間に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に直接伝えないようにする方法です。この技術は特に高層建築や病院などで導入されることが多く、建物内の振動を最小限に抑えることで、住人や利用者の安全を確保します。
加えて、これらの技術を最大限に活用するためには、日頃からの点検やメンテナンスも欠かせません。例えば、耐震構造が正しく機能しているか、制震装置や免震装置に劣化がないかを定期的にチェックすることが重要です。
また、住人自身も非常時の避難経路を確認したり、家具の固定や非常用持ち出し袋の準備など、地震に備えた具体的な対策を講じることが求められます。
◇台風・強風対策

台風や強風に対する住宅の備えは、家族の安全と財産を守る上で非常に重要です。まず、屋根や外壁の強化が基本となります。屋根は強風の影響を受けやすいため、瓦のひび割れやズレ、トタンのめくれがないか定期的に点検し、必要に応じて補修を行うことが大切です。また、外壁のひび割れや塗装の劣化を放置すると、雨水が侵入して建物の耐久性が低下するため、適切な補修を心掛けることが重要です。
窓の保護も欠かせないポイントです。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼ることで、強風時に飛来物が当たってもガラスの破片が室内に飛び散るのを防げます。また、シャッターや雨戸を設置することで、窓そのものを物理的に守ることができます。既存のシャッターがある場合も、定期的に動作確認を行い、必要に応じて修理や交換を行うことが推奨されます。
さらに、家の周囲の環境整備も大切です。庭やベランダにある植木鉢、物干し竿、ゴミ箱など、強風で飛ばされる可能性のあるものは、事前に室内に移動させるか、しっかりと固定する必要があります。側溝や排水口が詰まっていると豪雨時に排水が滞り、浸水の原因となるため、定期的な清掃を行い、水はけを良好に保つよう努めましょう。
◇水害・浸水対策

水害や浸水から一般的な住居を守るためには、いくつかの具体的な対策が有効です。
まず、建物への水の侵入を防ぐために、外壁や基礎部分に防水性の高い材料を使用することが重要です。特に1階部分の外壁を防水塗料で仕上げることで、浸水時の被害を軽減できます。
また、玄関や窓、換気口などの開口部からの浸水を防ぐために、止水板や防水シートを設置することも効果的です。これらは比較的簡単に取り付けられ、急な豪雨時にも迅速に対応できます。
さらに、敷地内外の排水溝や雨水枡を定期的に清掃し、詰まりを防ぐことが、雨水の適切な排出を確保する上で重要です。これにより、豪雨時の浸水リスクを低減できます。
また、分電盤や給湯器、室外機などの重要な設備を可能な限り高い位置に設置することで、浸水時の被害を防ぐことができます。これにより、設備の故障や感電リスクを低減することが可能です。
さらに、土のうや防水シートなどの防災用品を事前に準備し、必要時に迅速に設置できるようにしておくことも重要です。これらの対策を講じることで、水害や浸水のリスクを効果的に軽減し、安全な生活環境を維持することが可能となります。
◇耐火性能

さらに、耐火性能の高い建材を使用することで、火災発生時の延焼を防ぐ効果が期待できます。
これらのポイントを取り入れることで、安全で快適に暮らせる家づくりを目指しましょう。
【あわせて読みたい】
▼【補助金制度あり】熊本で賢く太陽光発電を導入!知っておきたいメリット
災害に強い家を建てるなら対策が重要

地盤調査は建築予定地の地盤特性を把握し、地震や浸水リスクを評価する重要な手順です。地盤調査を怠ると建物が不同沈下し、地震時の液状化による倒壊のリスクが高まります。床上浸水への対策として盛り土やかさ上げ、高床などの方法が有効です。
◇地盤調査の重要性
地盤調査は、建築予定地の地盤の強度や特性を把握するために行われます。地盤調査によって地震や浸水に対するリスクを評価し、適切な基礎工事を計画できます。家を建てる際に地耐力を調べる地盤調査は、建築基準法によって義務付けられています。
地盤調査には、「ボーリング調査」「SWS試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)」「平板載荷試験」などの種類があり、費用や調査制度に若干の違いがあります。
地盤調査をしっかりと行わなかった場合には、建物の一部が沈下して傾く「不同沈下」が発生する場合もあるため注意が必要です。また、地震が発生した際に地盤が液状化し、建物倒壊のリスクが高まることが考えられます。
◇床上浸水への対策

熊本は台風や集中豪雨による床上浸水が他県よりも多いエリアであるため、必ず床上浸水への対策を講じておきましょう。床上浸水への対策としては、盛り土やかさ上げ、高床などの対策が有効です。
・盛り土
盛り土は、建物を建てる前に地盤を高くするために、土を盛る方法です。盛り土をすることによって建物の基礎部分を周囲の地面より高くするため、浸水リスクを低減できます。盛り土には地盤の強度を補強し、建物の安定性を高める効能もあります。
・かさ上げ
かさ上げとは、建物自体を持ち上げて地盤面よりも高くする方法のことです。基礎部分をかさ上げで新たに強化することで、建物の寿命を延ばせます。
・高床
高床はお寺の本堂などによく見られる造りで、建物の床がテーブルの上に乗ったような形状をしています。高床にすることで建物の下部に空間ができるため、浸水の被害を受けにくくなるだけではなく、通気性も向上し、湿気対策としても有効です。
◇住宅の構造

特に地震による倒壊を防ぐためには、建物の耐震性能を示す「耐震等級」に注目することが大切です。耐震等級は1〜3までのランクがあり、数字が大きいほど耐震性が高いことを示します。最も高い耐震等級3の住宅は、大規模な地震にも耐えられる設計となっており、長期的な安全性を確保できます。
また、建物の形状も耐震性に大きく影響します。シンプルな形状の住宅ほど揺れを分散しやすく、負荷を軽減できるため、耐震性能が向上します。特に、1階と2階の間取りが揃っている総二階建ての住宅は、バランスが良く、揺れに強い構造の代表例といえるでしょう。
さらに、制震・免震構造を採用することで、建物の揺れを抑え、より安全な住まいを実現できます。地震に強い構造を選び、安心して暮らせる住まいをつくりましょう。
◇バランスの取れた間取り
柱や壁が少ない間取りは構造的に弱く、地震の揺れに対して耐性が低くなるため注意が必要です。例えば、大きな吹き抜けや広い開口部、2階部分がせり出したオーバーハング構造などは、地震時の負荷が大きくなりやすく、耐震性が低下する可能性があります。
そのため、できるだけシンプルでバランスの取れた間取りを選ぶことが、安全な住まいづくりにつながります。1階と2階の間取りが揃った総二階建てや、耐力壁の配置を適切に計画することで、地震時の揺れを分散させやすくなります。
また、造り付けの家具や収納を活用することで、大きな揺れによる家具の転倒を防ぎ、避難経路を塞ぐリスクを軽減することが可能です。間取りの工夫次第で、より安全で快適な住まいを実現できるため、慎重に検討することが大切です。
【あわせて読みたい】
▼地盤改良は必須?熊本の土地で知っておきたい地盤調査の基礎知識
災害時も安心して暮らせる設備と設計

災害が発生した際、安全に暮らし続けるためには、備えが整った住まいが重要です。停電や断水時に対応できる設備や、スムーズに避難できる動線設計、十分な備蓄スペースの確保など、防災を意識した住宅づくりが求められます。
◇十分な備蓄が可能な収納スペース
食料や日用品を備蓄できるパントリーや納戸があれば、水や非常食、生活必需品を計画的にストックでき、ライフラインが止まった際も安心です。限られたスペースの住宅では収納を削減しがちですが、防災の観点からは欠かせません。
広い収納スペースを確保できない場合は、床下収納や階段下スペース、キッチンの吊り戸棚などを有効活用するのも良い方法です。定期的に備蓄の見直しと管理を行うことで、万が一の災害時にも安心して暮らせる住まいを実現できます。
◇スムーズな避難を可能にする動線設計

玄関や勝手口など、2箇所以上の屋外避難ルートを確保しておくことで、万が一1つの出口が塞がれてしまっても安全に脱出できます。特に高齢者が住む住宅では、階段を使わずに避難できる動線を考慮し、バリアフリー設計を取り入れることが望ましいです。
また、避難経路には障害物を置かず、夜間の停電時にも安全に移動できるように足元灯や蓄光テープを活用すると安心です。スムーズな避難を可能にする動線を確保することで、万が一の際にも冷静に行動し、安全を確保しやすくなります。
◇停電・断水時にも安心なライフライン対策

災害時に電気や水道が使えなくなることを想定し、太陽光発電システムや蓄電池を備えておけば、停電時でも照明や家電を一定時間使用でき、安心して過ごせます。また、雨水タンクや非常用貯水タンクを設置しておくことで、飲料水以外にも生活用水として活用でき、断水時の不便を軽減できます。
さらに、ガスの供給が停止した際に備えてカセットコンロを用意しておけば、温かい食事を確保することも可能です。こうした設備を整えておくことで、ライフラインが途絶えた場合でも、安全で快適な生活を維持しやすくなります。
【あわせて読みたい】
▼大海建設が提案する耐震技術と快適性を兼ね備えた家づくりとは?
熊本で注文住宅を建てる際は住宅性能も重視しよう

熊本は寒暖差が大きいため、高気密・高断熱の家が適しています。これらの住宅は外気温の影響を受けにくく、冷暖房効率が向上し、電気代の節約が可能です。また、耐震性も重要で、長期優良住宅建築計画認定制度に基づいた家づくりが安心できる暮らしにつながります。
◇高気密・高断熱の家

熊本県は、夏の猛暑と冬の寒さが厳しく、年間を通じて寒暖差が大きい地域です。このような気候条件のもとでは、高気密・高断熱住宅が非常に適しています。これらの住宅は、外気温の影響を受けにくく、室内の温度を一定に保つことができるため、冷暖房の効率が向上し、電気代の節約にもつながります。
高気密・高断熱住宅の最大の特徴は、外気の侵入や室内の空気の流出を防ぐ構造にあります。これにより、夏は涼しさを、冬は暖かさを維持しやすくなり、冷暖房の使用頻度が減少します。その結果、エネルギー消費が抑えられ、省エネ効果が期待できます。
さらに、室内の温度差が小さくなることで、ヒートショックのリスクも軽減されます。ヒートショックとは、急激な温度変化により血圧が変動し、心臓や血管に負担をかける現象で、特に高齢者にとっては重大な健康リスクとなります。高気密・高断熱住宅では、家全体の温度が均一に保たれるため、こうしたリスクを低減できます。
また、気密性が高いことで外部の騒音が遮断され、室内の音も外に漏れにくくなります。これにより、静かな住環境が実現し、快適な生活が送れます。さらに、断熱性の高い窓や壁を使用することで、結露の発生が抑えられ、カビやダニの繁殖を防ぎ、健康的な室内環境が保たれます。
◇耐震性も重要

熊本は過去に大地震が発生した地域であり、耐震性の高い住宅を建てることが非常に重要です。そのため、家づくりを検討する際には、耐震性を重視した設計・施工を行う工務店やハウスメーカーを選ぶことが求められます。
特に、「長期優良住宅建築計画認定制度」に基づいて家づくりを行う業者であれば、信頼性が高く、安心して任せることができます。
長期優良住宅建築計画認定制度は、住宅を長期間にわたって良好な状態で使用できるようにすることを目的とした制度です。この制度では、住宅の耐久性、居住性、環境性能など、さまざまな基準が定められています。
認定を受けるためには、耐震等級2以上(建築基準法で定められた耐震性の1.25倍)を満たす必要があります。これは、地震が発生した際にも建物の損傷を最小限に抑え、居住者の安全を確保するための重要な基準です。
さらに、長期優良住宅は耐震性だけでなく、断熱性能や省エネルギー性能にも優れているため、快適性や経済性も高い特徴を持っています。これにより、地震に備えながら、年間を通じて住みやすい環境を実現できます。また、認定住宅は税制優遇や補助金の対象となることが多く、経済的なメリットも期待できます。
【あわせて読みたい】
熊本でおすすめの注文住宅会社を紹介
熊本の気候や風土に適した家づくりを手掛ける各社は、耐震性や断熱性に優れた高品質な住まいを提供しています。木の温もりを活かした住宅や、最新技術を取り入れた省エネ住宅など、それぞれの特徴を比較し、理想的な住まいを見つけましょう。
◇新産住拓株式会社

新産住拓は、熊本で累計6,000邸以上の施工実績を持つ注文住宅会社です。厳選した天然乾燥木材を使用し、プレカット工場で精密に加工することで、高品質な木の住まいを実現しています。
また、自社工場を活用することで品質管理を徹底し、熟練の職人技と最新技術を融合させ、細部までこだわり抜いた家づくりを行ってきました。さらに、最大30年の長期保証や定期点検を実施し、建築後も安心して暮らせるように充実したアフターサポートを提供しています。
| 会社名 | 新産住拓株式会社 |
| 所在地 | 〒861-4101 熊本県熊本市南区近見8-9-85 |
| 電話番号 | 0120-096-112 |
| 公式ホームページ | https://shinsan.com/ |
熊本の気候やライフスタイルに寄り添い、家族が長く快適に過ごせる住まいを作り出しています。
新産住拓株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇住友林業株式会社

住友林業は、木の魅力を最大限に活かした住まいづくりを行っています。独自の「PRIME WOOD」技術では、厳選された木材を丁寧に加工し、快適で美しい住まいを実現することが可能です。設計は完全自由設計で、ご家族の理想をかたちにすることを大切にしています。
| 会社名 | 住友林業株式会社 |
| 所在地 | 〒100-8270 東京都千代田区大手町1-3-2 |
| 電話番号 | 03-3214-2220 |
| 公式ホームページ | https://sfc.jp/ie/ |
また、住友林業独自の「BF構法」により、優れた耐震性・断熱性・耐久性を兼ね備え、安心して長く暮らせる住まいを提供してきました。さらに、最大60年の長期保証や充実したアフターサービスで、建築後も安心のサポート体制を整えています。木のぬくもりを感じながら、心地よい暮らしを叶えたい方に推奨の住宅会社です。
住友林業株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼【住友林業】熊本で森を感じる注文住宅を建てよう!木の家で始める快適生活
◇株式会社谷川建設熊本支店

谷川建設は、50年以上の歴史を持つ注文住宅会社で、国産檜を使用したこだわりの家づくりを行ってきました。特に、日本三大美林の一つである「木曽ひのき」を採用し、90年以上の歳月をかけて育った最高級の木材を使用することで、強く美しい住まいを実現しています。
| 会社名 | 株式会社谷川建設熊本支店 |
| 所在地 | 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-18-18 |
| 電話番号 | 0120-35-5171 |
| 公式ホームページ | https://tanigawa-group.com/ |
また、熟練の職人技と最新技術を融合させ、住む人のライフスタイルに寄り添った設計を提案しているのも特徴の一つです。品質だけでなく、家族が心からくつろげる「時間品質」にもこだわり、丁寧なヒアリングを重ねながら理想の住まいを形にしています。
株式会社谷川建設熊本支店について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
◇株式会社日本ハウスホールディングス熊本営業所
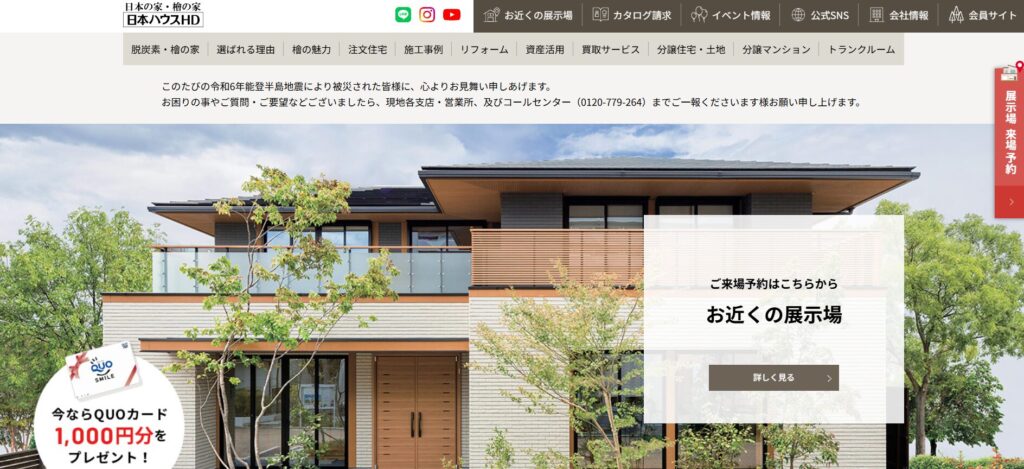
画像出典:株式会社日本ハウスホールディングス
日本ハウスホールディングスは、創業55年以上の歴史を持ち、耐震性・断熱性・デザイン性に優れた高品質な住まいを提供しています。特に、国産檜を活かした「檜品質」、高気密・高断熱を実現する「ゼロエネ品質」、健康で快適に暮らせる「快適品質」の3つを軸に、環境に配慮した住宅づくりを推進してきました。
| 会社名 | 株式会社日本ハウスホールディングス熊本営業所 |
| 所在地 | 〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍1-12-3 |
| 電話番号 | 096-377-8888 |
| 公式ホームページ | https://www.nihonhouse-hd.co.jp/modelhouse/pref/branch/?id=00370 |
また、業界トップクラスの断熱性能を誇り、ZEH基準を超える高い省エネ性能を実現しました。長期保証システムや24時間対応のサポート体制も充実しており、安心して長く暮らせる住宅メーカーです。
株式会社日本ハウスホールディングスについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼日本ハウスホールディングス 熊本営業所の評判とは?全国10万戸の信頼と檜の家
九州は自然災害が多い地域で、その理由は台風の経路であることや多くの活火山、プレートの境界に位置することにあります。過去には熊本地震や集中豪雨などの大規模な災害が頻発しました。
台風による風や豪雨による浸水は九州でよく見られ、特に風速が20m/sを超えると建物や屋根に被害を及ぼし、30m/s以上になると壁材や屋根材の飛散が起こります。浸水によっては家具や家電が損傷し、地盤の劣化も懸念されます。
地盤調査は地盤の強度や特性を把握し、地震や浸水リスクを評価する重要な手順です。また、床上浸水への対策も必要で、盛り土やかさ上げ、高床などが効果的です。
さらに、熊本では高気密・高断熱の家が適しており、耐震性も重要視されます。長期優良住宅建築計画認定制度に基づいた家づくりが安心であり、耐震性や居住性などの要件を満たすことが求められます。
熊本で家を建てるなら
当メディアおすすめハウスメーカーを見る

